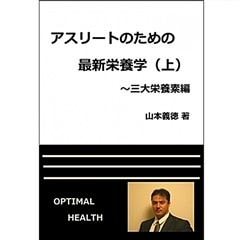タンパク質の分解 ~なぜ分解される必要があるのか~
掲載日:2018.11.01

私たちの細胞は代謝回転により、同化と異化を繰り返していると書きました。しかし同化は分かりますが、なぜ異化によって壊される必要があるのでしょうか。
オートファジー
一つには、「タンパク質を分解してエネルギーにしたり、食事からでは足りないアミノ酸を補ったりするため」です。これはタンパク分解系としては、「オートファジー(自食作用)」というシステムに分類されます。ノーベル賞で有名となりましたね。
ある研究によれば、血中アミノ酸レベルが高いときには、1時間あたり1%程度のタンパク質が分解されるに過ぎないのに、アミノ酸レベルが低くなると1時間あたり5%ものタンパク質が分解されてしまうとのことでした。
体内の栄養レベルが低いときにはアドレナリンやコルチゾル、グルカゴンなど「血糖値を上げる」ホルモンが分泌されますが、これらのホルモンはオートファジーを促進するため、タンパク質の分解が進んでしまうのです。
細胞質の一部が膜で囲まれて「オートファゴソーム」になり、それに分解酵素を含んだ「リソソーム」が働くと、オートファゴソーム内のタンパク質が分解されてアミノ酸が生じ、再利用に向かいます。
そして再利用されたアミノ酸はタンパク合成や糖新生、エネルギー産生に使われます。なお細胞内に入った細菌を分解するのもオートファジーの仕事の一つです。
逆に「血糖値を下げる」インスリンが分泌されていると、体内の栄養レベルは十分だと判断されるため、オートファジーは抑制されます。
なおアミノ酸の「ロイシン」がオートファジーを抑制するために有効だとされています。
ある研究によれば、血中アミノ酸レベルが高いときには、1時間あたり1%程度のタンパク質が分解されるに過ぎないのに、アミノ酸レベルが低くなると1時間あたり5%ものタンパク質が分解されてしまうとのことでした。
体内の栄養レベルが低いときにはアドレナリンやコルチゾル、グルカゴンなど「血糖値を上げる」ホルモンが分泌されますが、これらのホルモンはオートファジーを促進するため、タンパク質の分解が進んでしまうのです。
細胞質の一部が膜で囲まれて「オートファゴソーム」になり、それに分解酵素を含んだ「リソソーム」が働くと、オートファゴソーム内のタンパク質が分解されてアミノ酸が生じ、再利用に向かいます。
そして再利用されたアミノ酸はタンパク合成や糖新生、エネルギー産生に使われます。なお細胞内に入った細菌を分解するのもオートファジーの仕事の一つです。
逆に「血糖値を下げる」インスリンが分泌されていると、体内の栄養レベルは十分だと判断されるため、オートファジーは抑制されます。
なおアミノ酸の「ロイシン」がオートファジーを抑制するために有効だとされています。
ユビキチン・プロテアソーム系

そしてタンパク質を壊す理由のもう一つは、「タンパク質の品質管理」が理由となります。普通の工場でも不良品が作られたら廃棄されるように、体内でも不良品のタンパク質が作られたら、それを廃棄する必要があるわけです。
体内のタンパク質というと筋肉が真っ先に思い浮かぶかもしれませんが、実は酵素やホルモンなども体内で作られるタンパク質です。これらの不良品が出回ってしまったら、すぐに体調が崩れてしまい、命を脅かすことにすらなりかねません。
私たちの身体は、本来ならば厳密な品質管理によって、タンパク質が正しく合成されるようになっています。しかし水銀や鉛、ヒ素などの重金属に汚染されたり、また脳梗塞や心筋梗塞などで血液の流れが悪くなったりしても、タンパク質の合成に問題が生じてしまいます。このような事態に対応できるよう、不良タンパク質が定期的に壊されているのです。
さて不良品のタンパク質ができてしまった場合、まずは修復して正常に戻すように頑張ります。また、「どうも合成が上手くいっていない」と感じると、合成の途中でタンパク合成をストップさせます。しかしこれらの働きにも関わらず、不良品タンパク質ができてしまった場合、カラダはそれを「分解」しようとするのです。
そして困ったことに、構造上は品質的に問題が全くないのに、「不使用」の状態が長く続くと、やはり分解されてしまうのです。トレーニングをサボッていると、どんどん筋肉が落ちて行ってしまのは、こうしたワケです。
もともとトレーニングによって付けた筋肉は、生命活動にとっては不必要なもの。このようなものは優先的に壊されてしまいます。
では、どのようにしてタンパク質が分解されるのでしょうか。せっかく作ったタンパク質を、意味もなく無秩序に壊されてしまってはたまりません。
前述したオートファジーにおいては無秩序に分解されてしまう面もあるのですが、ユビキチン・プロテアソーム系においては、タンパク質は「選択的」に分解されます。まずは壊すべきタンパク質を標的として決めます。
標的が決まったら、そこに「ユビキチン」という76個のアミノ酸から作られた小さなタンパク質が結合します。これを「ユビキチン化」といいます。
ユビキチン化のときには、3種類の酵素が働きます。
そして壊すべきタンパク質が標的として定められると、そこにタンパク分解酵素である「プロテアソーム」が働いて、標的タンパク質が分解されるという流れです。
なおガンやエイズ、糖尿病、火傷、腎不全、敗血症のような状態だと異常なタンパク質ができやすく、カラダはそれに対応するため、ユビキチン・プロテアソーム系が活性化します。
また糖質コルチコイドやインスリン欠乏、酸化ストレス、PIF(タンパク分解誘導因子)などがこの系を誘導するとされます。
体内のタンパク質というと筋肉が真っ先に思い浮かぶかもしれませんが、実は酵素やホルモンなども体内で作られるタンパク質です。これらの不良品が出回ってしまったら、すぐに体調が崩れてしまい、命を脅かすことにすらなりかねません。
私たちの身体は、本来ならば厳密な品質管理によって、タンパク質が正しく合成されるようになっています。しかし水銀や鉛、ヒ素などの重金属に汚染されたり、また脳梗塞や心筋梗塞などで血液の流れが悪くなったりしても、タンパク質の合成に問題が生じてしまいます。このような事態に対応できるよう、不良タンパク質が定期的に壊されているのです。
さて不良品のタンパク質ができてしまった場合、まずは修復して正常に戻すように頑張ります。また、「どうも合成が上手くいっていない」と感じると、合成の途中でタンパク合成をストップさせます。しかしこれらの働きにも関わらず、不良品タンパク質ができてしまった場合、カラダはそれを「分解」しようとするのです。
そして困ったことに、構造上は品質的に問題が全くないのに、「不使用」の状態が長く続くと、やはり分解されてしまうのです。トレーニングをサボッていると、どんどん筋肉が落ちて行ってしまのは、こうしたワケです。
もともとトレーニングによって付けた筋肉は、生命活動にとっては不必要なもの。このようなものは優先的に壊されてしまいます。
では、どのようにしてタンパク質が分解されるのでしょうか。せっかく作ったタンパク質を、意味もなく無秩序に壊されてしまってはたまりません。
前述したオートファジーにおいては無秩序に分解されてしまう面もあるのですが、ユビキチン・プロテアソーム系においては、タンパク質は「選択的」に分解されます。まずは壊すべきタンパク質を標的として決めます。
標的が決まったら、そこに「ユビキチン」という76個のアミノ酸から作られた小さなタンパク質が結合します。これを「ユビキチン化」といいます。
ユビキチン化のときには、3種類の酵素が働きます。
そして壊すべきタンパク質が標的として定められると、そこにタンパク分解酵素である「プロテアソーム」が働いて、標的タンパク質が分解されるという流れです。
なおガンやエイズ、糖尿病、火傷、腎不全、敗血症のような状態だと異常なタンパク質ができやすく、カラダはそれに対応するため、ユビキチン・プロテアソーム系が活性化します。
また糖質コルチコイドやインスリン欠乏、酸化ストレス、PIF(タンパク分解誘導因子)などがこの系を誘導するとされます。
カルパイン系
筋肉が収縮するときは、筋小胞体というところからカルシウムイオンが放出されます。
トロポニンというタンパク質が筋収縮を調節しているのですが、これにカルシウムイオンが結合するとトロポニンの抑制が外れ、筋肉の収縮がはじまります。
このようにカルシウムイオンにはシグナル伝達としての働きがあるのですが、これにはタンパク分解酵素を活性化する働きもあるのです。
カルシウムイオンによって活性化されるタンパク分解酵素を「カルパイン」と呼びます。
ただしカルパインは必ずしもカルシウムイオンだけによって活性化されるわけではなく、ナトリウムイオンで活性化されるカルパイン3なども存在します。
筋肉は筋節(サルコメア)がいくつも繋がって筋原繊維を構成しています。
筋節どうしを区切っている膜をZ線と呼びますが、カルパインにはこのZ線のタイチンを分解してしまう働きがあります。大ざっぱな流れとしては、筋肉にまずカルパインが働いて筋節をバラバラにし、そこにユビキチン・プロテアソーム系が働いてペプチドにまで分解され、そこにリソソームが働いてオートファジーが行われるという経路が考えられています。(※15)
※15:Sepsis stimulates release of myofilaments in skeletal muscle by a calcium-dependent mechanism. FASEB J. 1999 Aug;13(11): 1435-43.
トロポニンというタンパク質が筋収縮を調節しているのですが、これにカルシウムイオンが結合するとトロポニンの抑制が外れ、筋肉の収縮がはじまります。
このようにカルシウムイオンにはシグナル伝達としての働きがあるのですが、これにはタンパク分解酵素を活性化する働きもあるのです。
カルシウムイオンによって活性化されるタンパク分解酵素を「カルパイン」と呼びます。
ただしカルパインは必ずしもカルシウムイオンだけによって活性化されるわけではなく、ナトリウムイオンで活性化されるカルパイン3なども存在します。
筋肉は筋節(サルコメア)がいくつも繋がって筋原繊維を構成しています。
筋節どうしを区切っている膜をZ線と呼びますが、カルパインにはこのZ線のタイチンを分解してしまう働きがあります。大ざっぱな流れとしては、筋肉にまずカルパインが働いて筋節をバラバラにし、そこにユビキチン・プロテアソーム系が働いてペプチドにまで分解され、そこにリソソームが働いてオートファジーが行われるという経路が考えられています。(※15)
※15:Sepsis stimulates release of myofilaments in skeletal muscle by a calcium-dependent mechanism. FASEB J. 1999 Aug;13(11): 1435-43.
[ アスリートのための最新栄養学(上) ]